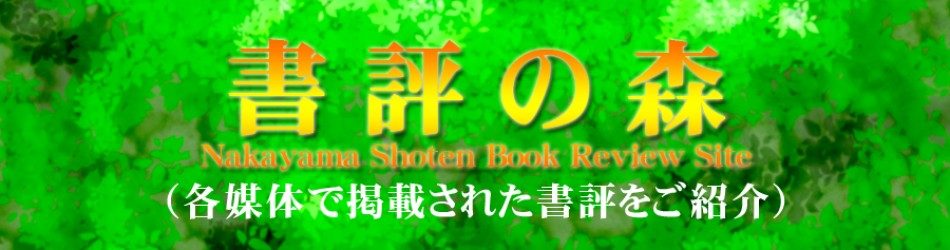循環器ジャーナル Vol.66 No.4(2018年10月号)「書評」より
評者:小川久雄(国立循環器病研究センター理事長)
世界でもトップレベルの長寿社会に入った日本では,今後医療問題が益々大きな課題となってくる.そして医療費という点からは,日本では循環器系疾患が20%と最も高い割合を占めている現状がある.なかでも心不全の増加が顕著であり「心不全パンデミック」と呼ばれるようになってきた.日本循環器学会では全国に1,353施設あるすべての循環器専門施設と協力施設212施設の合計1,565施設から循環器疾患診療実態調査 The Japanese Registry Of All cardiac and vascular Diseases(JROAD)を行い,2012年からは心不全患者の入院数も調査し21万人から2016年には26万人となっている.増加の程度は著明で今後もさらに増え続けると思われる.これは日本のみならず世界的な傾向でもある.
これに対して,日本循環器学会と日本心不全学会は関連11学会とともに「急性・慢性心不全診療ガイドライン(2017年改訂版)」を作成した.このなかには心不全の一般の方への啓発活動として,分かりやすい表現で「心不全とは,心臓が悪いために,息切れやむくみが起こり,だんだん悪くなり,生命を縮める病気」と定義されている.さらに日本循環器学会では日本脳卒中学会,さらに関連19学会と協力して「脳卒中と循環器病克服5カ年計画」を策定し発表したが,このなかでも心不全に注目している.特に予防の重要性も記載している.
本書は「循環器内科専門医バイブル」シリーズの第1巻「心不全─識る・診る・治す」として発刊された.シリーズ総編集,「心不全」専門編集とも小室一成東京大学循環器内科教授が行っている.先生は現在日本循環器学会代表理事でもあり,心不全をライフワークとして研究されてきた.そのネットワークを活用して素晴らしい執筆者を選ばれている.心不全の全体像や基礎研究からはじまり診断,治療,治療薬やデバイスの一歩進んだ使い方・使いこなし方,様々な病態に応じた治療,さらに今後の新しい治療薬と治療法に関して,非常に詳細にかつ分かりやすく記載されている.
心不全は病因が多岐に渡り,病態も様々である.治療も効果的な薬剤やデバイスが多く,その選択も重要である.救急疾患としても多いが慢性疾患としても重要である.さらに最適な治療は何か,根本的な治療法は,と聞かれて明確に答えられない場合もある.本書は図や写真もふんだんに使われ,循環器専門医のみならず,専門医を目指す若い医師,さらには一般医にも理解できる内容となっており,現時点で伝えるべき最新の内容も盛り込まれている.読者の方の心不全の理解,診断や治療に役立つ教科書といえる.ご活用を切に御願いする次第である.
タイムリーな企画と刊行:心不全─識る・診る・治す
内科 Vol.122 No.3(2018年9月増大号) Book Reviewより
評者:友池仁暢(公益財団法人日本心臓血圧研究振興会附属榊原記念病院)
日々の臨床実践に役立つことを目指した新しいシリーズ「循環器内科専門医バイブル」が企画され,第1巻として「心不全」が刊行されました.心不全は世界的にパンデミックと言われるほどの広がりを見せています.わが国の循環器疾患の有病者数は脳血管障害を除いても総人口の9.2%を占めています.その特徴は年齢が高齢化するほど有病率が高いこと,循環器疾患の原因は遺伝性,先天性,生活習慣関連,感染等々と多彩ですが,その終末像は押並べて心不全に陥ることです.したがって,心不全の診断と治療の本質をきちんと理解して日常臨床に臨むことは臨床医にとって基本中の基本になりつつあります.本書は,循環器専門医と専門医を目指す若手医師に留まらず臨床に携る医療者が渇望していた「心不全の座右の書」ではないかと思います.
心不全は臨床医にとって捉えどころのない暖昧な病態であると受け止められています.例えば,心不全の分類がいくつもあること,病態の説明が様々に繰り広げられていること,内科治療薬としてのジギタリスと利尿薬の位置付けがEBMの時代になって何度も疑問視されたことなど,枚挙にいとまがないほどです.このような情勢も踏まえて日本循環器学会と日本心不全学会は合同で心不全に関するガイドライン2017年版改訂を公表しました.その中で,一般の人達が治療の機会を逸して重症化,あるいは難治化に陥らぬよう「一般向けの定義」もメディアに公開しています.専門医の学会によるかつてない画期的な取り組みです.このガイドライン2017年改訂版を深く理解し日常の臨床に活かす上で本書は優れた羅針盤でもあります.
本書の専門編集の小室一成教授は,重層化し錯綜する概念の座標軸を見事に整理し,最新の知見を包括的に理解できるように,病気の本質を「識る」ことから説き起こし,正確に「診る」ことによる病態の理解,幾多のパラダイムシフトを経た「治療法:治す」の提示と何を選択すべきか,ベッドサイドで必要とされる判断と指針を実務に役立つように本書を組み立てられています.序章に始まる全6章は,わが国のエキスパートが専門医にとっても関心の高い具体的なテーマについて,全体像を俯瞰しつつ個別課題の解決のために正確かつポイントを外さない記述をしてくださっています.
心不全は病院の規模や専門領域に関係なく日常の臨床でよく遭遇する疾患になった今,「心不全一識る・診る・治す」の刊行は時宜にかなったものと言えましょう.臨床現場で日々出てくる疑問に納得のいく答えを求める臨床医にとって本書は期待通りの情報と判断の迷いや悩みに対する的確なアドバイスを与えてくれるに違いありません.