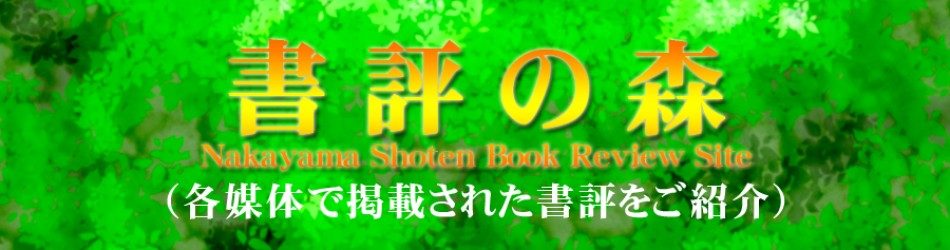評者:小川純人(東京大学大学院医学系研究科老年病学)
近年、呼吸器疾患の分野でも漢方薬の効果と可能性に注目が集まってきており、かぜ症候群、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患、嚥下性肺炎など、西洋医学によるアプローチだけでは必ずしも十分な効果が得られにくい症状や病態に対して、漢方薬は補完的な治療選択肢、相性の良い併用薬として活用されてきている。本書「呼吸器病の漢方治療ガイド-プライマリ・ケアで役立つ50処方」は、実地医家を含めた医療従事者が呼吸器疾患の診療・ケアに従事する際の実践的な漢方医学の手引き書でもあり、全編にわたりビジュアルに富む構成で非常に読みやすい内容になっている。
本書の特徴は、まず第一にイラストや図表を活用した解説のわかりやすさにある。漢方治療の総論と各論に大別され、前者では呼吸器疾患診療における漢方医学の考え方や診察方法などがイラストとともに解説されている。後者では、代表的な呼吸器疾患に対する漢方医学・漢方薬の活用が豊富なイラストや症例とともに具体的かつわかりやすく示されていて、初学者にもイメージしやすく抵抗なく読める工夫が随所に施されている。
さらに注目したい点として、呼吸器疾患に頻用される約50種の漢方薬について、理解しやすい患者イメージ図に加えて、構成生薬、効能・効果、使用目標などが証の考え方に基づいて丁寧に紹介されていることが挙げられる。また、西洋薬と漢方薬との併用における可能性や安全性、患者への説明ポイントなど、外来や病棟をはじめとする実臨床の現場で実際に生じうるポイントや疑問にも具体的に答えてくれる内容となっている。こうした実践的な情報が満載であるゆえに、忙しい診療の間であっても十分に活用できる点も秀逸である。
呼吸器疾患の診療に際して、多彩な症状や症候を抑えたり整えたりするアプローチは、患者のQOL向上にもつながり重要である。本書を通じて、症状、体質、体力などの要素を組み合わせた証に基づく考え方が一層浸透し、実臨床における漢方医学や漢方薬の効果的な活用につながることが期待される。
本書は、漢方医学や漢方薬処方の経験が浅い若手医師や研修医だけでなく、西洋医学や西洋薬を中心に呼吸器疾患診療を担っている医師や医療従事者にとって、診療の幅を広げてくれ頼りになる一冊となるだろう。
評者:巽 浩一郎(千葉大学医学部 呼吸器内科)
現在の保険診療では保険病名から診断をつけて,その診断名に沿った薬物療法をする.こうした医療は自宅のパソコンに向かって症状を話せば処方箋を入手できるといったAI診断などの実装化,医療DX(デジタルトランスフォーメーション)の導入に親和性がある.さて,呼吸器内科を含む内科を標榜している医療機関には冬季,相当数の急性感染症の患者が来院する.インフルエンザである場合は抗インフルエンザ薬,細菌感染症が疑われる場合は抗菌薬,診断名に沿った薬を処方する.「風邪をひいたみたいなので何かお薬をください」とお願いされることも頻繁にあるが,「かぜ症候群」には治療薬がないので,処方は対症療法となる.著者が丁寧に取り上げているこの「かぜ症候群」には漢方治療では多様な選択肢があり,漢方治療のおもしろさ,奥深さを知っていただくにはとても良い例と思う.
著者は本書冒頭で「漢方薬は基本的に病名ではなく,いくつかの症状,体質,体力などの要素を組み合わせた証という概念を基本として投与する.この証の概念の理解が難しいため投与すべき漢方薬がなかなかひとつに絞り難いことがある.」と述べている.漢方治療に慣れていない読者に向け,第1章『漢方治療総論』では「かぜ症候群」を例に漢方の考え方,望診・聞診・問診・切診,舌診・脈診・腹診といった診察法を用い漢方薬を選択する,医師の判断の流れをわかりやすく伝えてくれている.そこをしっかり読むと漢方治療の基本がわかり,第2章『漢方治療各論』で疾患別に具体的な処方が学べ,第3章では漢方薬の構成生薬,効能・効果,使用目標=証の解説でその理解が深まる.もちろん西洋医学的治療を否定するものではなく,併用例が多数紹介されており,「+漢方薬」の効果にも説得力がある.本書を手引きに漢方治療を実践できるようになるという仕掛けである.
漢方治療は,全人的医療(心身一如の治療),全身の調和を図る医療,診断即治療の医療である.西洋医学的治療では診断に関係のない徴候は主診断からみると捨てることになる(併存症としては扱うかもしれないが).漢方治療では,可能な限りの徴候を拾って病態診断に結びつける.生体を有機体として統合的に認識する.病気でなく病人を診る.AIに簡単にとって変えられない医療のおもしろさと奥深さがある.
この本を手に取った時点で,先生は漢方治療に理解と興味を持っているはず.この本を手掛かりに,もう一歩漢方の世界に踏み込んで欲しい.きっと別の世界観が見えてくるだろう.