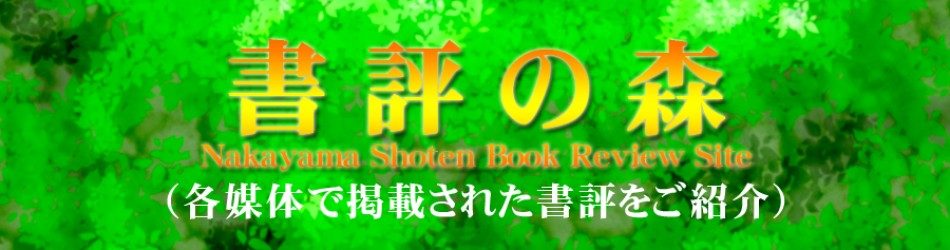内科 Vol.126 No.5(2020年11月号)「Book Review」より
評者:伊藤 裕(慶應義塾大学医学部腎臓内分泌代謝内科教授)
内科医が患者さんに「親身」になれる極意の書
もともと,医学は患者さんの痛み,苦しみを取り除く術として生まれた.そのために,患者さんが何をどう感じているか,その症状を虚心坦懐に聞くことが,医学の基本である内科の原点であることは言うまでもない.カナダの内科医,世界の医学教育に大きな影響を与え,私の母校の大先輩,聖路加国際病院名誉院長,日野原重明先生が敬愛してやまなかった,ウィリアム・オスラー(1849~1919年)も,“Listen to the patient. He is telling you the diagnosis”としている.
しかし果たして,私たちは患者さんの話を聞くだけで診断名を語ってくれていると思えるであろうか.
私は常々,教室員によい医者であるためのたった一つの秘訣として「親身」になることをあげている.私は「親身」に「Sym-Me」という英語をあてて,自己と同一視することとしている.その患者さんが自分の親だったらどうする? 自分だったらどうしてほしい? と考えて初めてなすべき医療がみえてくる.そんなことは当たり前と言われるかもしれない.実際,ほとんどの医者は親身になって診療にあたろうとしているはずである.しかし,現実にはその実現が難しいのは,親身になるためには専門的な知識が必要だからである.曖昧な知識があるだけでは,自信がもてず,他科の先生に紹介することになる.医師としてそれは誠実な対応かもしれないが,患者さんからすれば見放されたような印象になりかねない.いったん心理的な壁ができてしまうと,患者さんは自分が気になること全てをその医者に伝えようとしなくなり,そうなると我々は自分の専門領域の診断も正確に行うことができなくなる.私は,日野原先生が命名された「生活習慣病」を専門としている関係上,患者さんの生活習慣全般を理解し,患者さんが生涯にわたって付き合おうと思ってくれることが大切なので,この点はとくに重要である.
皮膚科がご専門の宮地良樹先生が編まれた『内科医が知っておくべき疾患102』は,内科医が患者さんに「親身」になれるための書である.この書に厳選された症状は,日常の内科外来できわめてよく遭遇するものであり,我々内科医が日ごろ患者さんから訴えられるものである.長年,患者さんを目の前に鋭く観察を続けてこられた皮膚科の宮地先生ならではの,まさに慧眼であると思われる.
内科外来で患者さんがこうした症状を訴えれば,「私の専門外ですし,専門の先生に診てもらってください」と言いがちである.「知っておくべき疾患」ではないと言い切るような内科医の先生もおられるのではなかろうか.しかし,そうした内科医は結局,「親身」な医療を実践できないのではと危惧する.本書に書かれた「ジェネラリストにとっての知識」をもっていれば,患者さんの訴えを怖がらず,門前払いせずに聞くことができる.そして,専門家への適時的なコンサルトも可能になる.
さらに,この本には各科のスペシャリストから内科医への適切なアドバイスが惜しみなく,それこそ「親身」になされている.それは,内科の専門化,細分化が批判される昨今,“本来ジェネラリストとしてあるべき内科医が,患者さんの状態を理解し,正しくできる医療を臆せずにやってください”という応援歌だと思う.間口の広い,患者さんから信頼される内科医,そして,他科との垣根を低くして,うまく連携できる内科医のための極意書として本書はあると考える.
人工知能(AI)の進歩で医師の職域は徐々に駆逐されていくのではないかという畏怖がある.しかし,患者さんの一断面の情報をつなぎ合わせるAIにはできない,患者さんに起こる様々な出来事をつぶさに知り,そのうえで日々変わっていく患者さんの人生の「物語」を語れる医師には,なかなかAIは追いつけないと思われる.そのような医師になるために,私はこの本を大切にしたいと思う.