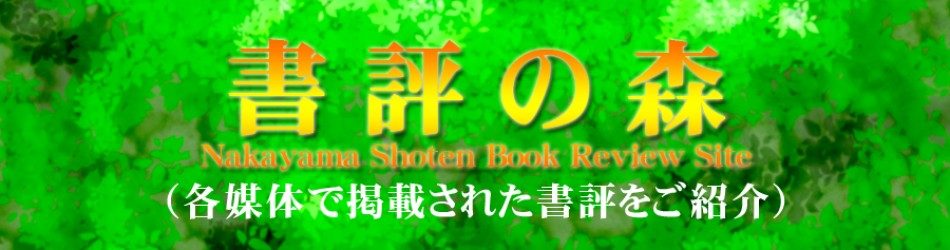わが国を牽引する高水準の糖尿病診療および療養指導をQ&A形式で体系的に示
プラクティス Vol.34 No.5(2017年9月号)
書評者:本田佳子(女子栄養大学栄養学部医療栄養学研究室)
朝日生命成人病研究所の高水準の診療並びに療養指導は,多くの人が認める事実であるととともに,医療者自身が自らの診療および療養指導のモデルとして研鑽の目標に定めているとの声を聞く.本書はその診療と療養指導のモデルが,Q&Aと解説というかたちで体系的に示された書籍である.そして,朝日生命成人病研究所の糖尿病診療並びに療養指導のエッセンスを,本書からうかがい知ることができる.
執筆陣は朝日生命成人病研究所附属医院での実臨床で活躍する医師とスタッフを中心とし,ガイドラインあるいは教科書にはない,日々の診療の疑問から質問(Q)130あまりを厳選し,それによって療養指導の体系化を図っている.CONTENTSに示されているChapterは「I. 糖尿病の考え方」「II. 検査・治療・療養指導」「III. 食事療法・食事指導」「IV. 運動療法・運動指導」「V. 薬物療法・薬物指導」「VI. 合併症の検査・治療・療養指導」「VII. 妊娠や小児・思春期の糖尿病,特殊な病態での糖尿病治療」「VIII. 療養指導を行う環境づくり・療養指導に役立つ社会的知識」となっている.まるで目の前の患者と向き合うがごとく,診療と療養指導が展開される質問(Q)が連なり,興味をもってどんどん読み進むと,そこには体系化された治療と療養指導への「教育」が織り込まれていることに気づく.監修者および編者の「現場で役立つ実践的な書籍をつくろう」とする熱い思いが伝わってくる.
糖尿病は,診断は比較的容易であるが,治療は難しい.一言で糖尿病といっても,慢性疾患で長い経過をたどるため患者一人ひとりの病態やステージは大きく異なっている.また,患者自身による自己管理がたいへん重要だが,自己管理自体が患者の負担となる.個々の患者の生活や病態を把握し,何が自己管理を困難にしているかを考え,患者とともに治療と療養指導を進めるにあたり,その要となる医療スタッフ全員に求められるチームの連携のありかたの優れたモデルが,ここに示されているのである.
また,随所にCOLUMNやTopicsを加えている.「膵島関連自己抗体」「GAD抗体測定法の変更に伴う対応」「SMBGの精度」「責任インスリンとは」「サルコペニアを予防するための食事指導・運動指導」「ウォーキング10,000歩/日の根拠」「造影剤の使用時にビグアナイド薬を休薬する理由」「低血糖の体への影響」「血糖の変動,HbA1cの変動と合併症の関係」「糖尿病患者に心電図検査を実施する際の注意点」「胎内環境と肥満の関係」「エンパワーメントとは?」など,いまさら同僚や先輩に質問するには躊躇する疑問への解説,そして今日的な診療や療養指導にとどまらず,さらに先を見据えた診療や療養指導へと読者を牽引している.
朝日生命成人病研究所が日本の糖尿病診療や療養指導をリードし続けてきた真髄となる「患者さんと家族を支え,糖尿病をもっていても合併症を起こさず,糖尿病をもたない人と同様に人生を全うできるよう支援することを任務とする」医療人としての姿勢を,初心に返って学びうる貴重な書籍である.