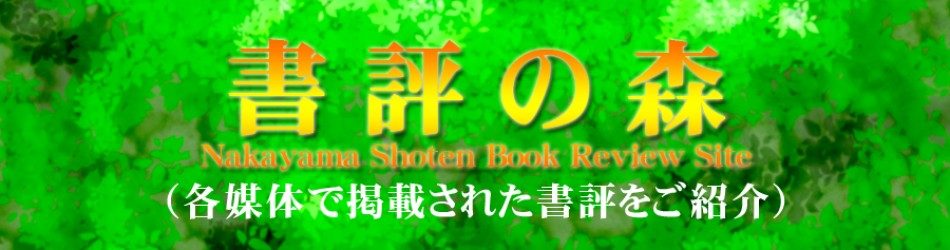内科 Vol.128 No.5(2021年11月号)「Book Review」より
わが国の脳卒中医療の現状を映す鏡
評者:戸田達史(東京大学大学院医学系研究科神経内科学教授)
国内多施設での登録事業「日本脳卒中データバンク」が活動を始めてから20年余が過ぎました.本事業を創始された小林祥泰先生(島根大学名誉教授)を中心に数年ごとに解析結果をまとめて出版されるのを,これまで楽しみに読んできました.数年前に国立循環器病研究センターに管理運営が移管されたと聞き及んでいましたが,移管後初めてのまとめとなる最新版「脳卒中データバンク2021」が,今春刊行されました.「脳卒中・循環器病対策基本法」も法制化され,一般市民の方々の脳卒中への関心も高まる中で,時宜を得た企画といえます.
脳卒中は戦後の一時期,国民の最大の死因であり続け,現在でも約300万人の有病者をかかえる国民病です.一命を取り留めても高度の後遺症を遺す患者も多く,国民の健康寿命の延伸に大きな障碍となります.発症後早期に脳組織を不可逆的に損傷させるため,長年にわたって有効な治療法を欠き,治らぬ病気とみなされた時期が続きました.しかし今世紀に入ってt-PA静注療法(静注血栓溶解療法)や経皮的な機械的血栓回収療法の開発,脳画像診断の進歩などに伴い,飛躍的に治療成績を高めるようになりました.そのような脳卒中診療の転換期であるこの約20年のデータをふんだんに掲載した本書は,まさに「わが国の脳卒中医療の現状を映す鏡」といえましょう.
本書では,2018年末までに登録された急性期脳卒中(脳梗塞,脳出血,くも膜下出血),一過性脳虚血発作の患者20万例弱の臨床情報を,多くの分担執筆者が独自の切り口で解析しています.たとえば脳卒中は何歳くらいで多く発症するのか,どのくらい重症で,どのくらいの割合で後遺症を遺し,また自宅復帰できるのか,そのようなごく単純な疑問にも,十分な症例数で回答を示しています.興味深いテーマごとに解析された結果は,多数のグラフや表で示されており,視覚的にもわかりやすいものになっています.
わが国には,脳卒中や認知症,頭痛,てんかんなど,非常に多くの患者を有する神経疾患がありますが,その正確な発症者数や臨床転帰を把握するのはなかなか困難です.脳卒中においては,前述した対策基本法に基づく全国患者登録が早晩始まるそうですが,全国の患者を悉皆性高く収集するにはまだ相当の時間を要するでしょう.そのような中で脳卒中医家はもとより,一般開業医の先生方やふだん神経疾患を診る機会の少ない医師,脳卒中のリハビリに携わる医療スタッフの方々などにも,本書をお手元に置き,あるいは電子版を端末に載せ,脳卒中に関して湧き上がる疑問を解く参考書として,ぜひ役立てていただきたく思います.
medicina Vol.58 No.9(2021年8月号)「書評」より
評者:宮本 享(京都大学医学部附属病院長)
「脳卒中データバンク2021」には,1999年に研究開始された日本脳卒中データバンクに,日本全国の130を超える施設から登録され蓄積された約17万例の急性期脳卒中の臨床情報解析が掲載されている.
本書の第1部には,日本脳卒中データバンクの概要とデータ分析が記載されている.まず,脳卒中に対する医療政策を行うにあたって,本邦における脳卒中のデータベースがないことが大きな問題であることに20年以上前に注目し,本事業を立ち上げられた小林祥泰先生をはじめとする先達の慧眼に深甚なる敬意を表したい.標準化された診断名と評価尺度に基づいて登録された精度の高いデータに基づく分析であり,経年変化などの分析は本邦における脳卒中の変遷を示す貴重なデータと考えられる.
つづいて第2部では,疾患や病態,治療法その他のテーマごとに,日本脳卒中データバンクに登録された膨大な症例をもとに分析と解説がなされている.各項目の冒頭には,わかりやすくサマリーが箇条書きに掲載されている.
さいごに第3部では,日本脳卒中データバンクを用いた研究論文についての解説がなされており,本書は「本邦における最近20年間の脳卒中医療のとりまとめ」といってよい内容となっている.豊田一則先生を中心とした「国循脳卒中データバンク2021編集委員会」の皆様のご尽力に感謝したい.
2018年12月に「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中,心臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本法」いわゆる脳卒中・循環器病対策基本法が成立し,循環器病対策推進基本計画が策定され,悉皆性がある脳卒中・循環器病の情報をどのように収集していくかということが,現在検討されている.多数の治療施設が全国に分散していて均てん化が求められ,急性期医療であり,地域連携で転院をしていく脳卒中の登録には,治療施設が集約化されており,データ登録に時間的余裕がある「がん登録」とは異なる課題がある.今後,循環器病対策推進基本計画に基づく登録事業を成功させるうえでも,日本脳卒中データバンクのこれまでのノウハウは大変貴重な経験であり,それをまとめた本書を,本邦における脳卒中医療従事者には是非精読していただきたい.