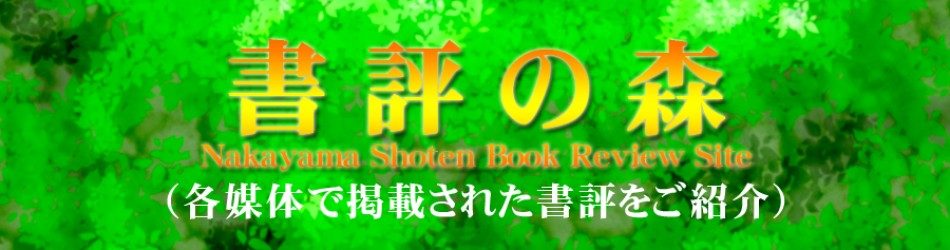評者:渡辺雅彦(東海大学医学部外科学系整形外科学教授)
整形外科開業医や一般病院勤務医の先生方は,すべての整形外科受診患者さんに対応をしなければならない.しかしながら,ご自分の専門領域外のことも多く,一言に整形外科といっても対象とする疾患やその治療法は多種多岐にわたり,また日々進歩していて,知識のupdateには非常にご苦労されていることと推察する.《ニュースタンダード整形外科の臨床》はそのような臨床の場に役立つ,広範にわたる整形外科疾患の診断と治療法を網羅した指南書である.編集委員である田中栄先生,松本守雄先生,井尻慎一郎先生が各領域のエキスパートである専門編集員を指名し,総論と各論で11のテーマについてシリーズを形成している.第4巻の本書もそうであるが,各論の多くに「痛みと障害」というタイトルが付けられているところが興味深い.患者さんは決して疾患名では受診されずに,その方その方の独特な表現で愁訴を語られ受診される.まずは臨床に即した「症状ありき」が,このタイトルから伺え,通常の教科書の「疾患ありき」と一線を画しているシリーズであることが分かる.臨床の場で患者さんの愁訴を聞き,本書を紐解く,そういった書物と言えよう.
さて,シリーズ4巻目,各論1巻目は『頚椎・胸椎の痛みと障害』,「診断の精度を上げ,患者満足度を高める」として群馬大学大学院医学系研究科整形外科学教授の筑田博隆先生が専門編集をお務めになり,今回めでたく上梓された.
1章では「診察の基本」として外来での診察のポイントがまとめられている.本章では,診断書の記載および障害等級の評価の留意点や指定難病等についての記載もあり,専門外の先生方にとってまさに親切なガイドブックとなっている.2章は「検査・診断の基本」であるが,診察手技や各種評価法,また特にMMT評価のコツは,動画も付属してポイントが再確認できる.3章「首(肩甲帯)の痛み」,4章「上肢の痛み・しびれ」,5章「背中の痛み」,6章「外傷による首・背中の痛み」,7章「筋のやせ,手に力が入らない」,8章「麻痺・歩行障害」,9章「斜頚・首下がり」,10章「背骨の変形」と各論が続くが,患者さんが訴える愁訴はほぼカバーできているように思う.また頚椎捻挫等,外来診療で対応に苦労することが多い疾患は特に丁寧な記載がされており,外来診療の強力な応援ツールになっている.
筑田博隆先生にはガイドラインや種々の委員会で御指導を頂いてきた.先生のお話は常に理路整然としているが,先生の日々の臨床も理路整然と「診断の精度を上げ!」を実践されているのだと思う.種々の愁訴から,理路整然とした思考過程と手順でその原因・病態を正確に導き出すこと,最も大切なことである. 本書がその一助となり,すべての整形外科医にとって,使い勝手の良い,無くてはならない,首と背中の病気の指南書となることを信じている.